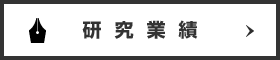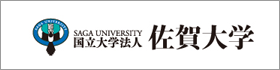研究概要
本研究室では、自己組織化、メゾスコピック構造、オプトエレクトロニクスをキーワードに、将来の情報社会基盤技術となるであろうフォトニクスデバイスやクリーンエネルギーである太陽電池の開発を目指して研究を進めています。
詳しい研究概要はこちら![]()
当研究室の最新の研究の詳細につきましては、新着情報において逐次更新してまいりますので、そちらをご覧下さい。
新着情報はこちらから
高性能有機半導体の開発
高性能の有機半導体素子を実現するためには、高いキャリヤ輸送性を有する有機半導体分子を開発するだけではなく、それを秩序正しく配列する必要があります。
我々は、
- Marcus理論とGaussian Disorder Modelによる実験的研究から高性能の有機分子構造の設計指針を確立すること
- 自己組織化を利用した凝集構造の秩序化による高性能化
の二つの面から高いキャリヤ輸送性を有する有機半導体を開発するための基礎研究を進めています。
具体的には以下のような研究を行っています。
- Marcus電子移動理論とGaussian Disorder Model に基づいた高性能有機半導体設計

- 液晶性を用いた自己組織化による有機半導体の凝集構造制御と高移動度半導体材料の開発

- 有機無機ペロブスカイトの自己組織化による有機半導体の凝集構造制御と高移動度半導体材料の開発

新規構造を有する太陽電池の開発
現在、原子力に代わる、再生可能でクリーンなエネルギー源の開発が求められています。我々は、これまでの有機半導体や有機無機ナノナイブリッド研究をバックグラウンドとして、シリコンベースの太陽電池に取って代わる新しい太陽電池の開発を行っています。具体的には以下の研究を行っています。
- 分子内電荷移動構造を有する有機半導体を用いた太陽電池の開発[近日PDF公開予定]
- 有機-無機ペロブスカイトを用いた太陽電池の開発[近日PDF公開予定]
有機-無機層状ペロブスカイト量子井戸材料を用いた
フォトニクス材料の開発
有機-無機層状ペロブスカイト化合物は無機半導体層と有機層が交互に積層した量子井戸構造を自己組織的に形成する化合物群です。これらは、その低次元半導体構造に基づいた電子的光学的特性を示します。また、有機層に機能性発色団を導入することで多様な量子井戸材料を構築することができます。これらの特性を利用して新しいオプトエレクトロニクス材料開発のための基礎研究を行っています。
- 有機-無機層状ペロブスカイトの基礎光物性評価

- 高品質な有機-無機層状ペロブスカイト薄膜作製法の開発

- 有機-無機層状ペロブスカイトを用いた発光デバイスの開発

- 有機層に機能性発色団を導入したハイブリッド量子井戸材料の構築と新規フォトニクス素子への応用

- 有機-無機層状ペロブスカイト量子井戸LB膜を用いたキャビティポラリトンレーザ

量子化学計算による材料設計
現在では、パソコンの性能が飛躍的に向上したため研究室レベルでも量子化学計算により、かなりの精度で物質の物性を予測することができるようになりました。我々も、GaussianやGamess等の量子化学計算用ソフトを使い、物性評価をし、より効率良い材料開発研究を進めるための研究を行っています。特に、キャリヤ移動度や光非線形性に着目し研究を行っています。
その他の研究
以上の研究以外にも、レーザ核融合用シンチレータ色素の開発、レーザ色素や有機EL用色素の開発など分野にとらわれず自分の能力を活かせる分野へ積極的に研究を行っています。